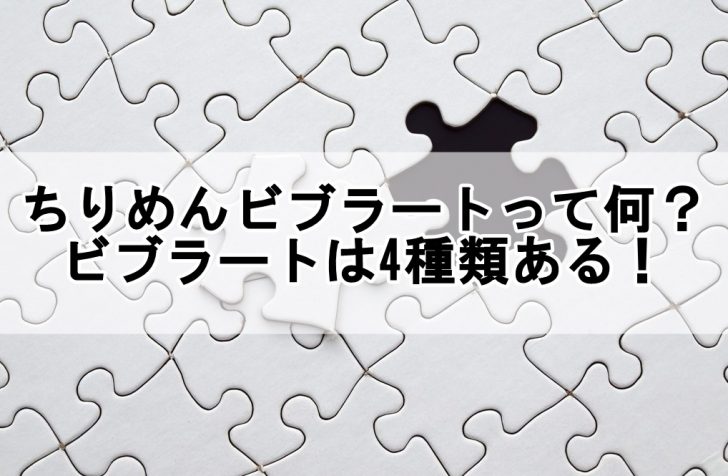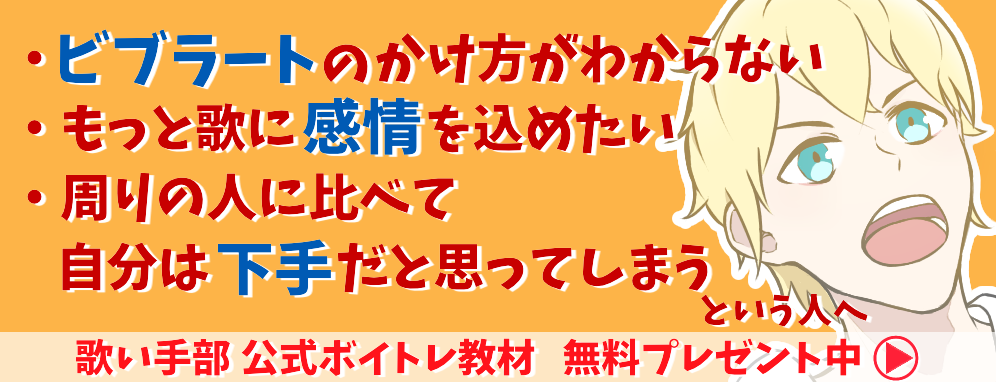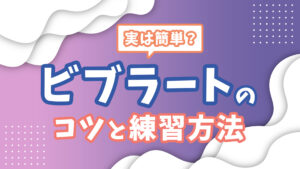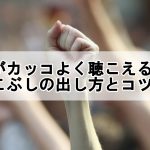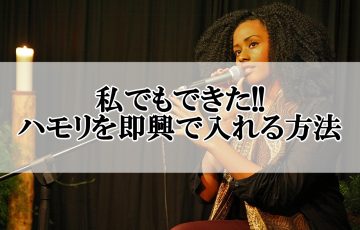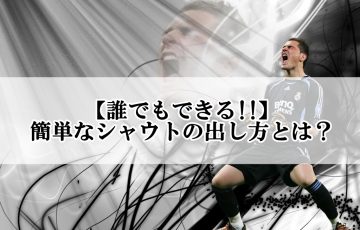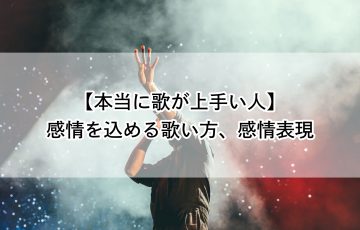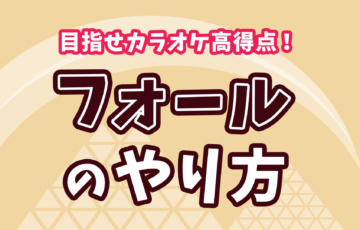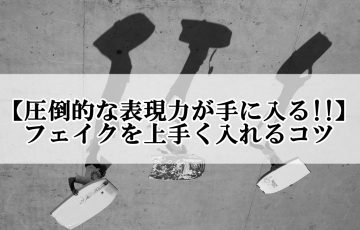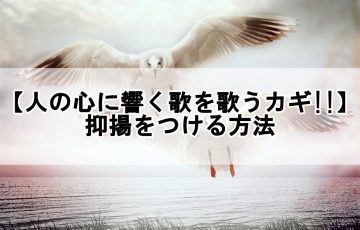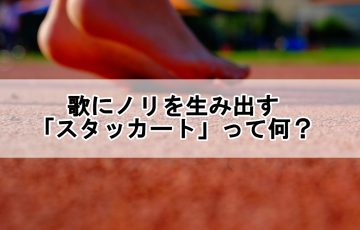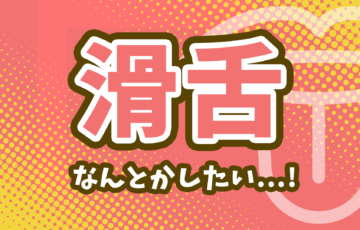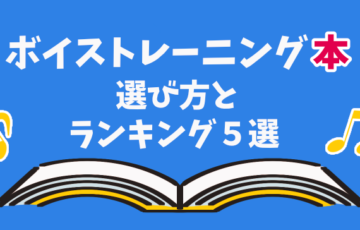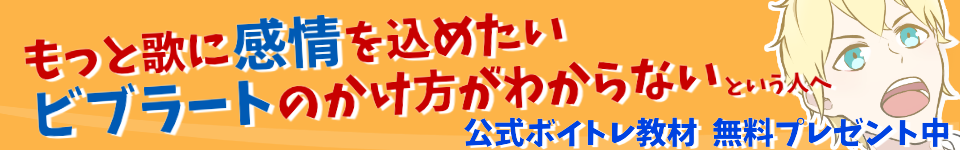一言でビブラートと言っても、
ビブラートには大きく分けて4種類あります。
ちりめんビブラートというのも、
その中の1つです。
それぞれのビブラートに個性があり、
聴いている側の印象が大きく変わります。
この4つのビブラートを使い分けることで、
表現の幅がグーンと上がります。
ということで、今回は
ビブラートの種類についてお話します。
ビブラートとは?
ビブラートについて、
簡単におさらいしたいと思います。
ビブラートとは、ある一定の音を保ちながら
音を上下に揺らすテクニックです。
フレーズ・サビの終わりや間奏の前などで
よく使われるテクニックのことでした。
ビブラートについてもっと詳しく知りたい、
ビブラートのかけ方も知りたい方は
こちらの記事をご覧ください。
ビブラートの種類
ビブラートはどんな間隔で上下させるか
どれだけ音を上下されるかで聴こえ方が変わります。
例えば、音を上下する間隔が短いと、
ワンワン響くようなビブラートになります。
かなり自己主張の激しいビブラートですが、
ビブラートをかける時間が短い時に使いやすいです。
このように、波の間隔と揺れ幅を変えることで
いろんな種類のビブラートができます。
間隔と揺れ幅でビブラートは無数にあるため、
正確には4種類と言うことはできません。
ただ、今回はわかりやすく説明するために
4種類に分けてお伝えします。
間隔の長短と揺れ幅の大小の組み合わせで
4つのタイプができます。
Aタイプ:間隔が短い+揺れ幅が小さい
このタイプのことを
ちりめんビブラートと言います。
緊張して震えている声と似ていて、
不安定でコントロールできていないように聴こえます。
そのため、ちりめんビブラートは
使わない方が良いと指導する方もいます。
確かに、ちりめんビブラートしか
出せないのであれば改善した方が良いでしょう。
ただ、個人的には
ちりめんビブラートも良い味があると思うんです。
例えば、宇多田ヒカルさんは
ちりめんビブラートを魅力的に使っています。
他にも、GACKTさんも
ちりめんビブラートをよく使っています。
ひとつのテクニックとして、
出せるようにしておくに越したことはありません。
Bタイプ:間隔が短い+揺れ幅が大きい
ワンワン聴こえるのが特徴です。
ターザンが綱を渡っている時の
「あ~ああ」という声に近いです。
伝統音楽や民謡などで
使われることが多いビブラートになります。
Cタイプ:間隔が長い+揺れ幅が小さい
このタイプがJ-POPなどでよく使われ、
最もスタンダードなビブラートになります。
聴き心地が良くて、
サビの余韻を出すのにもってこいです。
Dタイプ:間隔が長い+揺れ幅が大きい
あなたは演歌を聴くことがありますか?
演歌の歌い方やビブラートって
かなり特徴があると感じるでしょう。
J-POPやアニソンを演歌の歌い方で歌うと、
かなり違和感があるはず。
このタイプのビブラートは
演歌でよく使われるビブラートなんです。